平成は30年で幕を閉じた元号です。私は1987年12月生まれで、平成元年には1歳、平成2年には2歳と、年齢が元号の年数とほぼ一致していました。そのため、平成には特別な愛着を感じています。
世間では「失われた30年」と呼ばれ、暗いイメージを持たれることも多いようですが、私にとっては本当に良い時代だったと感じています。
その思いからか、数年前に書店で『平成史』という本を見つけたとき、つい手に取って購入しました。今日は雨で万博の予定を変更したので、この本をじっくりと読み進めたいと思います。
- 歴史としては短すぎる
- バブル崩壊後のITバブルへ
- 東日本大震災に阪神・淡路大震災などの災害
- 日本経済が謳歌した時期は1955年〜1991年 平成3年まで
- アメリカとロシアとの冷戦終焉後のグローバルの波に乗り切れなかった日本
- 冷戦期こそ日本が繁栄していた時期となる
日本経済を押し上げていたのは紛れもなく製造業
1965年の東京オリンピックからバブル崩壊までの1992年までがモノづくり職人が多かった模様
すごいのが
1955年〜73年の間の年平均のGDPは10%というから驚きを隠せない
2025年GDP関連予測の比較
以下に、主要機関の予測をまとめます(カレンダー年または財政年度ベース):
| 機関 | 予測対象 | 実質GDP成長率 | 名目GDP(兆円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 財政年度2025 | +1.2% | 629 | 公式政府見通し |
| IMF | カレンダー年2025 | +1.1% | – | 実質成長率のみ提供 |
| 日本銀行(BoJ) | 財政年度2025 | +1.1%(中央値) | – | 範囲+0.9~+1.1% |
| 大和総研 | カレンダー年2025 | +1.6% | – | 「成長のゲタ」含む |
| 三菱UFJリサーチ | 財政年度2025 | +1.2% | – | 詳細はレポート参照 |
1%程度しかないっていうレベルになっちゃったって感じですな
ベルトコンベアー式工場の普及こそが日本経済を支えた
概要
ベルトコンベアー式の工場は、アセンブリライン方式を用いた製造施設で、製品がコンベアベルト上で順番に組み立てられる効率的な生産方法です。
このシステムでは、多くの労働者が高賃金で雇用され、強力な労働組合が賃上げを達成します。
高賃金による購買力が大量生産された製品の販売を支え、企業の収益と労働者の高賃金を維持するサイクルが形成されます。男性労働者の雇用と賃金が安定すると、かつて工場や農場で働いていた女性は専業主婦となり、子供は労働せずに教育を受ける現代家族が広まります。
さらに、労働組合の政治的影響力により福祉制度が整備され、働かない女性や子供は夫の社会保障に加入し、完全雇用と高賃金による税収や積立金で財源が賄われます。
社会・経済への影響
このシステムは、労働者の生活水準を向上させ、家族構造や社会保障制度に大きな影響を与えます。男性の安定した収入により、伝統的なジェンダーロールが強化され、女性の家庭内役割が増す一方で、子供の教育機会が拡大します。また、福祉制度の整備は社会全体の安定を支え、経済的な繁栄を促進します。
歴史的背景
このモデルは、20世紀初頭のフォーディズム(Fordism)に似ており、ヘンリー・フォードが自動車製造でアセンブリラインを導入した際に発展しました。この時期、労働者の高賃金が消費を支え、経済成長を加速させました。
バブル崩壊と共に変わる経済縮図
このシステムは市場に出回る製品が大量生産品となり画一的なものとなってしまう
当時の生産技術や情報技術では生産や流通ラインの変更は難しく多様化に向けて舵を切ることができなかった
そこで登場したのが大手広告会社とマスコミとなる

購買力を上げるためにありとあらゆる手段を講じて宣伝しまくるという作戦
当時のドラマなんてステマの嵐だった笑
これにより「新しい流行」や「新しい話題」を振り撒くことになった
平成は、そういった生産力が成熟しそして衰退しいく過程で生み出された商品に対してあらゆる付加価値をつけて
売り出していた時代とも言えるかもしれない
ポスト工業化社会とは
ポスト工業社会とは
ポスト工業社会は、経済が製造業から主にサービス業や知識ベースの産業に移行した社会の段階を指します。この概念は1970年代に社会学者ダニエル・ベルによって広められました
ポスト工業社会は、サービス部門が製造部門よりも多くの富を生み出す社会の開発段階である」と定義されています。
以下の表は、ポスト工業社会の主要特徴と例を整理したものです。
| 特徴 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| サービス部門の優位性 | サービス部門がGDPと雇用の大部分を占める | アメリカ(77.6%、2021年)、日本(71.39%、2022年) |
| 知識経済 | 知識と情報が資本として重視され、経済成長の原動力となる | ソフトウェア開発、金融分析 |
| 雇用の変化 | ブルーカラーからホワイトカラーの専門職へのシフト | IT専門家、医師、銀行家 |
| 技術進歩 | 情報通信技術の進歩が生産性と革新を推進 | 自動化、デジタル化 |
| グローバル化 | 国家間のつながりが深まり、経済活動に影響を与える | グローバルサプライチェーン |
| 都市化と情報ハブ | 都市が情報交換と経済活動の中心となる | ニューヨーク、ロンドン、東京 |
- 製造業からサービス業への移行。
- 知識と情報の重要性の増加。
- 雇用パターンの変化、専門的・技術的仕事の増加。
- 経済的変化に伴う社会構造の変化。
情報技術が進歩し、グローバル化も進む。
そうなってくると日本を拠点として製造していたものを人件費の安い海外に工場を建てることになった
機械が熟練工並みの仕事をしてくれだしその人を雇い続ける必要もなくなった
大事になったのは、企画を立てる少数の中核社員や現場にいる単純作業の期間工
IT技術の台頭によりますます生産ラインが小規模へとなり随時変更も効くようになった
広告もダイレクトメールやホームページになっていき
今までのテレビCMでの宣伝効果もどんどん薄れていっている
ポスト工業化となった次の流れが非常に面白い
流通や販売のコストが下がる
販売網と製品の多様化が相まってこれにより消費者に安く多様な商品が提供される
選択肢の幅が広がるので流行が発生しにくくまた流行ってるものに対してのアンチというのも
多様化として処理されるようになる
ここまでの下りだと一般国民にとっては安く色々なものが手に入り、どんなことをして楽しんでもそれは多様性として社会から受け入れられるといういい事づくしに見える
が
これは商品だけでなく仕事も多様性が求めれるようになり
福祉の財源であり前提だった正規雇用が減少する事態になる
これにより、賃金のベースアップなどを要求するような人材が不足し労働組合が衰退
国が福祉に財源を回すことができず国民は自力で生きていかなければならない状況へとなっていく
そうなると歳いけばいくほど格差が生じてしまう
企業側としては、最低限の優秀な人材だけを確保すればいいという発想になるので
粘り強く物事に取り組めるという一定の評価を下せる学歴という部分を重視するようになる
となると反対に低学歴だと人生ハードモードになると考えるのが親
子供に対して大学進学へと促すように思考を巡らす
学校の勉強だけではなく、塾にも通わせなければいけなくなる
塾も当然ビジネスなのでそれなりの月謝を要求してくる
そうなってくると専業主婦ではやっていけなくなり女性の労働力が上昇する
これにより家族形態が揺らぎ選択可能性の増大が男女関係にも及ぶので離婚率が増える
失業と非正規雇用が増えた平成の犠牲者
若年層で特に増加した
これがいわゆる就職氷河期言われれる世代
就職氷河期は1993年から2005年頃の就職難期で、この時期に新卒で就職活動を行った世代
2025年現在、これらの人々は43歳から55歳の範囲にいると考えられている
スキルのない若者より経験者が雇用されやすいことが一つの要因と考えられる
限られた正規雇用の座をめぐり競争激化
就職が決まらないと収入と雇用が不安定なため結婚が困難となり、親元同居が長期化し
晩婚化と少子化が進む
オレって一体なんなんやろ?っていう俗にいうアイデンティティーの模索の時期が20代で終わらないために
「青年期の長期化」が生じる
不安定とリスク感の増大のためうつ病などが増加する
20代後半の頃はバーの女マスターにご飯を食べさせてもらっていた
元彼に似てるっていうのが理由だったと言っていた
後に紹介してもらったけど俺よりも全然男前でむちゃくちゃ恥ずかしかった
そんな彼女がある時教えてくれた
28歳の考え方はこれから生きる上でベースになるみたいやで
あれから10年近く経つけど確かに考え方はあまり変わってない
なんなら好みの女性までも変わってないまであるかもしれないw

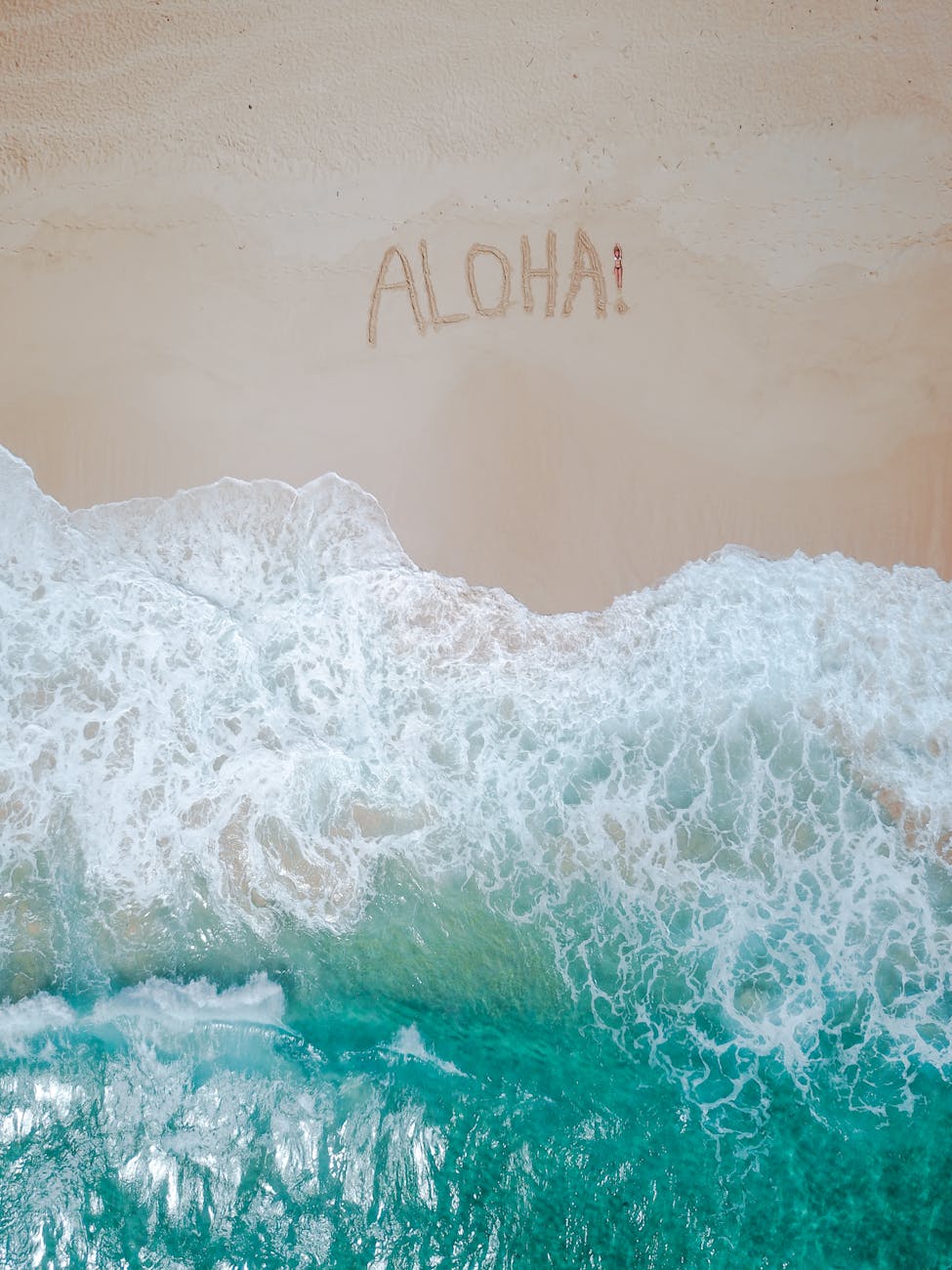
コメントを残す